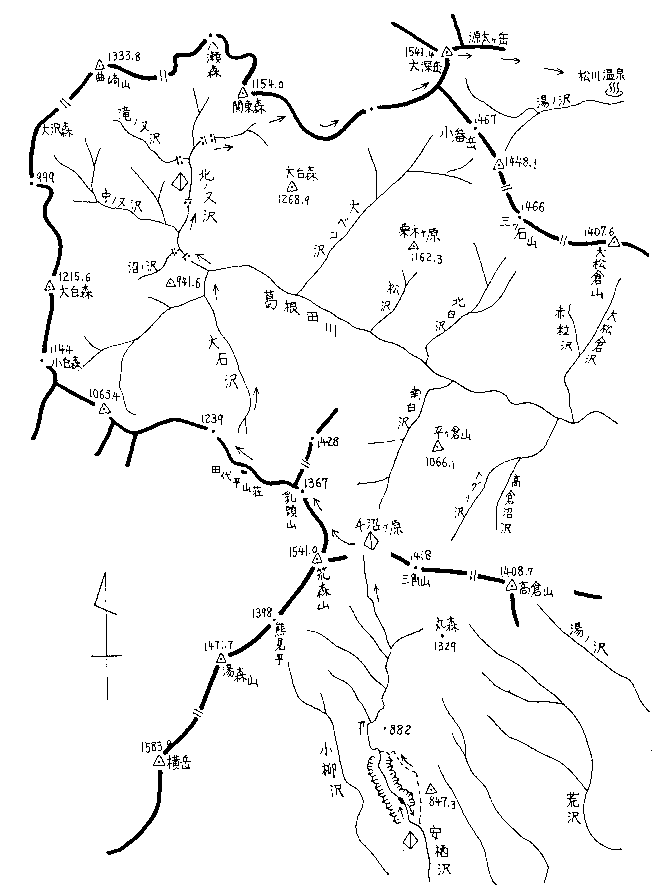発行日 1982年10月1日 |
安栖沢(アヅマイ沢)
東北 / 葛根田川・北ノ又沢へ1981年8月13日〜16日
メンバー:鈴木(利)、(L.鈴木(清)、藤井、柘植)
安栖沢から千沼ヶ原へ抜け、乳頭山を経て葛根田川支流の大石沢を下降し、同
じ川の北ノ又沢を溯った後、大深沢を下るという計画を立てていた。しかし、こ
の地域の沢の情報が乏しく、安栖沢溯行に2日要した為、大深沢下降を中止して、
大深岳経由で松川温泉へ下山した。
今回の沢は全体的に滝が少ないが、川幅が広くて距離がある為、スケールの大
きさを感じさせられた。人の入谷もほとんどなく、沢の中では大石沢の釣師以外
には出会わなかった。お盆の大移動の時期に静かな沢歩きが出来、本来の山の中
での生活を多いに楽しみまた味わうことが出来た。
8月13日(木) 晴れ 安栖沢(488mまで)
安栖沢は、秋田駒ヶ岳から乳頭山へ続く稜線の東面を流れる沢で、千沼ヶ原を水源とし、
雫石から葛根田川と合流し、雫石川となる。
無人駅の赤淵で下車し、国道を田沢湖方面へ進み、安栖部落から安栖沢沿いの林道へと
入っていく。沢の流域から源頭の山々まで低く連なり、高度を感じさせないのはいかにも
東北らしい。
1/2.5万の地形図によると、小柳沢方面へ続く山道が沢の422m地点を横切って
いるので、それを利用するつもりでいたが、踏み跡が見つからず薮をこぎ、沢の348m
地点まで強引に下った。結局、唯一の情報通り、下流の砂防ダムから入るのが最上のよう
だ。
422mの吊橋まで15分、更に1時間15分ほどして、単調な河原歩きに飽きてきた
頃、右岸から30m位の滝を持つ荒れた沢が合流する。ここの先からいよいよ長いゴルジ
ュ帯となる。滝は3m前後の小さいものしかないが、水量が多い為か深い釜が多く、両側
は高い絶壁が続いている。
渡渉を繰り返しながら暫く進むと、3mの滝に出合う。釜が深くて取り付けないので、
右壁の斜上するバンド沿いにアンザイレンし、落ち口まで下降した。その後30分近く釜
やトロを進むと、釜のある3m滝に阻まれた。両側は問題にならない程切り立った岩なの
で、泳いで滝に取り付くしかない。何度か試みたが、水流に押し返されてどうしても滝に
達することができない。そこで、高巻けそうなところを探しながら戻っていったが、壁の
上に出られるルートは全く見当たらず、ついにゴルジュを抜けてしまった。登りで苦労し
た釜のある3m滝は、アプザイレンして飛び込み、泳いで渡った。
既に3時半となり、体も濡れていたので、流木の多い488mの小さな二俣になった河
原に露営をすることにした。
【コースタイム】
赤淵駅 6:40 → 安栖沢(348m) 9:07/25 →
ゴルジュ入口 11:55 → 3m滝 12:10/13:30 →
釜(引き返し点) 14:00 → 3m滝上15:25 →
TS(488m) 15:50
8月14日(金) 晴れ 安栖沢(488mから千沼ヶ原)
安栖沢を中止し、大深沢に転進するという案もあったが、薮こぎの大高巻きを覚悟して、
予定通り千沼ヶ原を目指すことにした。左岸の支流を詰め、P701を通り850m位ま
で尾根上のところを登ってからトラバース気味に進み、918と882のピークの中間の
ガレを持つ沢に出た。ゴルジュも終わっているようなので、沢沿いに下ることにした。最
初は滝を巻いて左岸の尾根を辿ったが、その後一部アップザイレンをやりながら沢沿いに
下り、再び本流(710m)に立つことが出来た。トラバースでは根曲竹に苦労し、実に
3時間半の高巻きだった。
ここから千沼ヶ原まで高度差にして650mであるが、滝のない緩い傾斜が続く為、距
離は長い。時々岩魚がいそうな奇麗な淵に遭遇するのが唯一の慰めとなった。千沼ヶ原ま
で5時間半の淡々とした歩行を続け、流れがブッシュに覆われるようになった頃、ニッコ
ウキスゲの群生した草原に出る。そして、その先には千沼ヶ原の素晴らしい湿原があった。
【コースタイム】
TS 5:55 → P701 6:30 → 下降開始点 9:00/10 →
本流(710m) 9:40/10:10 → 921m二俣 11:50 →
999m二俣 12:45 → 1100m二俣 13:30 →
1218m二俣 14:20 → 千沼ヶ原15:35
8月15日(土) 晴れ後曇り 乳頭山→大石山→北ノ又沢(800m)
すがすがしい朝の尾根歩きの後、乳頭山の山頂からの眺めも気持ち良い。
ここから、葛根田川から分岐し、乳頭山の北面から山頂へ突き上げている大石沢の下降
が始まる。田代平山荘の少し先の湿原から薮を掻き分けていった。源頭の薮はあまりなく、
比較的楽に沢に入ることができ水流もすぐに出現した。最初は大岩のゴーロ帯であったが
一歩先の景観を楽しみに下っていた。ところが、台風の影響であろうか、大変な荒廃であ
る。至る所に倒木や枯れ枝が横たわり、何ヶ所か両岸が崩壊した形跡も見られる。おまけ
に周辺のブナ林が害虫にあらされて無残に枯れ、青い幼虫の死骸が大量に水中に浮かんで
いた。
リーダーが3年前にこの沢を登った時は、滝のない静かな奇麗な沢であったらしく、以
前と同じ沢とは思えないと強調していた。沢や川は自然の力で大きく変動してしまうのだ
からその威力はすさまじい。
期待外れの荒れ沢で、精神的にも参りかけてきた頃、戸撃沢の合流点あたりから広い大
きなナメ床となり、それが葛根田川本流まで続いている。今までの不満も一掃してしまっ
た。源頭から3時間15分の行程だった。
“葛根田川”それは素晴らしい景観を呈した川だ。742mの出合い付近は広い川幅に
澄んだ黄緑色の水が蕩蕩と流れ、それがどこまでも続いているかのようだ。溯るにつれ、
河原もなくなり、両岸に茂った木が水面に写る為かグリーン系統の絵の具を何本使っても
困難と思われるような彩色のファンタジックな世界が広がっている。この辺は、沢が屈曲
を繰り返す毎に変化があって期待あふれる所だ。
沼ノ沢出合いの少し下流で、久々に滝が出現した。5mの快適に登れる滝である。沼ノ
沢からは15mの奇麗な滝が流れ込んでいる。ここを過ぎるとナメの中ノ沢と合流する。
この辺までは河原もなく、なめの連続する楽しい沢歩きが出来、行程もはかどる所だ。左
岸から20m滝を有した無名沢を見送ると、前方を2段25mの大滝に立ち塞がれる。せ
っかくの滝であるが左岸の踏み跡沿いに巻く。落口から下を覗き込むとさすがに迫力があ
る。この上で3m位の小さな滝を越えると河原が所々に開けてくる。大滝から5分程の8
00m地点の右岸の河原を本日の最終点とした。
【コースタイム】
千沼ヶ原 6:20 → 乳頭山 7:00/30 →
田代平大石沢源頭 8:05/20 →
葛根田川出合 13:35/12:00 →
沼ノ又沢出合 12:30 →
2段25m滝 13:05/10 → TS 13:15
8月16日(日) 晴れ 北ノ又沢(800m)〜大深岳
大深沢下降を中止し、稜線から大深岳へ向かうことにしたため、沢も東方へルートを取
り、大白森でなく関東森の東側に出ることにした。
平凡な河原歩きを20分程続けると、滝ノ沢出合いに着く。滝ノ沢からは大滝が木々の
間から覗き、比較的テント場に良い所だ。857mの二俣を右俣に入っていくと、すぐに
15mの滝があり、右岸を高巻く。次の4mの滝も登れそうもないので、降りないで更に
大高巻きをした。最初のうちは踏み跡らしきものがあったが、何時の間にか消えてしまい
ブッシュに掴まりながらの大格闘となった。ルートファインディングの末、2つめの尾根
沿いにブッシュを頼りに下り、最後の2ピッチは懸垂で沢に降り立った。
この後、ナメが出現してきて楽しくなり行程もはかどる。一時間で985mの二俣に来
る。左俣へ入るのだが、出合いには25mx10mのナメ滝がかなりの勾配で落ちている。
初めのうちはフリクションを利かせて快適に登れるが、最後は更に傾斜が増したので、右
壁のブッシュを頼りに登った。しかし、二人は上まで一気に登れたようだ。
かなり源頭も近づいた感じであるが、更にナメ滝が続き快適である。所々にブッシュが
出てくるようになっても相変わらずナメ床で歩き易い。最後の1060mの分岐を左へ行
くと20分ほどで水もなくなり、更に根曲竹の急斜面を10分ほどかき分けると、はっき
りしない縦走路に出た。
しかし、道とはおよそかけ離れていてボサがひどく、大半は根曲竹の薮となっており、
稜線に出てからは苦痛の3時間であった。途中の2つの大きな湿原が唯一の慰めとなった
が、小畚岳と大深岳の間の主稜線に出ても期待に沿うような道ではなかった。
源太ヶ岳から松川温泉まで一気に下り、温泉に入って長旅の疲れを癒した。
【コースタイム】
TS(800m) 5:40 → 滝ノ又沢出合6:02/15 →
滝の大高巻き 6:50/8:05 → 958m分岐9:05/10 →
稜線 10:30/50 → 大深岳13:45/14:00 →
源太ヶ岳 14:20/45 → 松川温泉15:50/17:30 →
盛岡19:20
(鈴木(利) 記)
電子化 作野
【遡行図】